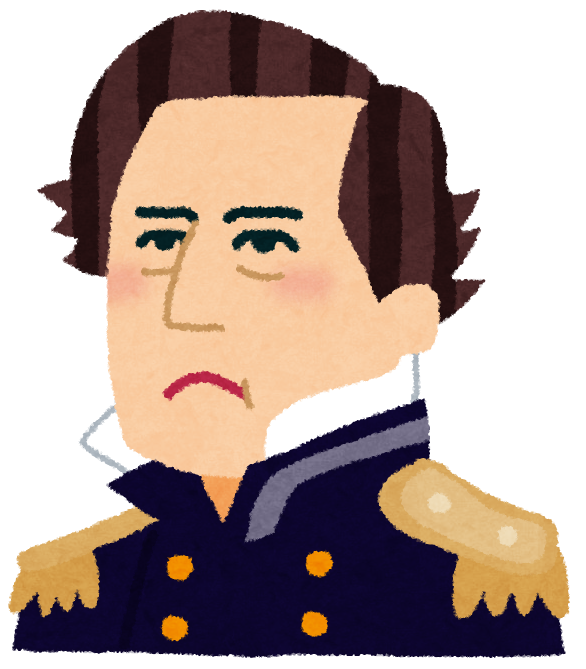
おい、市之丞。
同期のA君はあんなに仕事できるのに、お前だけだよ仕事がそんなに遅いのは…
社会人として恥ずかしくないの?
こんなひどいこと…言われた経験はありませんか?

はい…おなじみの、拙者が以前パワハラ上司から言われたパワハラ語録です(笑)
こんなこと言われると、心がポキッと音を立てて折れちゃいますよね…笑
拙者も以前はそうでした。
人から言われたことをいちいち気にして

嗚呼…拙者って嫌われているのかもしれんでござる。
本当いつまでも仕事がうまくできないのは、拙者に才能がないからでござるな…
仕事向いていないのかもしれない…
いっそのこと辞めたほうがいいのでござるか…
こ〜んなネガティブな考え事をしょっちゅうしていました(笑)
現代人って忙しいので、頭の中がいろんなことでごちゃごちゃなんですよね…
頭の中が絶念でごちゃごちゃしていると、余計なことまで考えてしまうのです。
そんな時におすすめしたいのが「日記」です!!
「…え?そんなありきたりなん?」
と思ったそこのあなた!
あなどることなかれ!
日記には、メンタルや脳に良い影響を及ぼすという研究もたくさんあるんですよ!
現に、拙者も日記を習慣化して書くようになってから、思考が整理整頓されていくような感覚となり、前述したネガティブな思考をしづらくなったと効果を実感しております!
それでは、今回も拙者の苦しい経験から得た経験を思い出しながら、行ってみましょう😂
日記の歴史
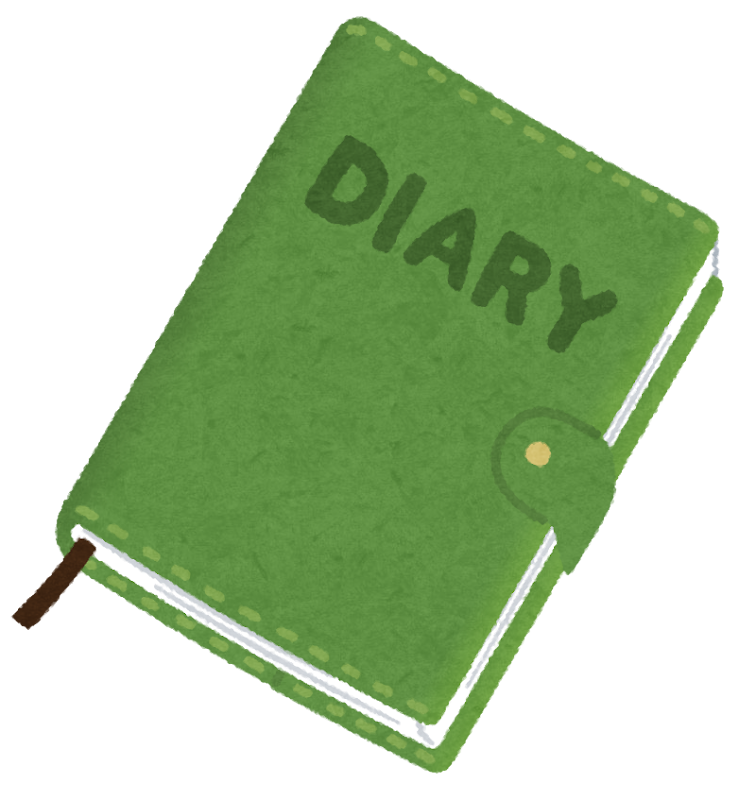
そもそも日記とは、いつから書かれているの?
素朴な疑問、調べてみました!
古代(紀元前〜紀元後初期ころ)
最古の日記のような記録は、古代エジプトやメソポタミアの粘土板などに残された業務記録・天候・出来事のメモなどに見られます。

これらは、現代でいう日記の概念とは異なり、出来事の「記録」という形で残されているものが中心だったようですが、これらが日記の起源と言っても過言ではありませんね!
中世ヨーロッパ(5〜15世紀ころ)
修道士たちが書いた「修道院記録(年鑑・出来事記録)」が現代に通ずる日記の起源的なものになります。
その後、ルネサンス期(14世紀ころ)以降になると、貴族や文学家の間で出来事への感想や思想などを綴る、現代のような日記が増えていきました。
日本の歴史〜平安時代(794〜1185年ころ)〜

日本では世界的に見ても非常に早くから「個人の日記文学」が発展しました。
特に貴族階級の女性たちによる文学的日記が知られています。

中でも有名なのは、皆さんもご存知の「紫式部」ですよね!
宮中での生活、人物観察、自己分析的な記述などが現代の日記の起源となったと言われています。
日記って、古代から脈々と続けられているものであることがわかりましたね。
それほど、日々の出来事を書き記すという行為は、我々人間にとって必要なことだったと言えるのだと思います!
それでは、本題の日記がメンタルにどのような影響を及ぼすのか見ていきましょう。
日記がメンタルに与える3つの効果

日記を書くことは、メンタルを守るために非常に効果的な「心のお掃除」です!
特にパワハラなどの精神的ストレスにさらされているときには、心の整理・自己肯定感の回復・ストレス軽減に大きく貢献します。
日記の効果をまとめると以下のものになります!
- 感情のラベリング効果
- ストレス軽減と免疫力向上
- 自己認識と自己肯定感の向上
それでは、ひとつひとつ効果を見ていきましょう!
感情のラベリング効果
カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究で、「自分の感情に名前をつけること(「悲しい」とか「嬉しい」とか)で、脳の扁桃体(不安・恐怖を感じるところ)の活動が抑制され、冷静になれる」という研究結果が示されました。
その研究では、「怒り」「悲しい」「悔しい」など、今自分が抱える感情を日記に書くだけで、脳のストレス反応が軽減されることが示されました。
【主な研究結果】
- カリフォルニア大学ロサンゼルス校2007年の研究
- 自分の感情を言葉で表現することで、身体のストレス反応が低くなった。
- 脳の扁桃体(感情を司る部分)の活動が抑制された。
- 胸がドキドキするなどの生理現象が抑制された。
- 感情のラベリングをした被験者たちは、「気が楽になった」と報告している。

普段、何気なく書いている日記も、科学的にひも解けばこのような効果があったんですね!
ストレス軽減と免疫力向上
心理学者ジェームズ・W・ペネベーカー(James W. Pennebaker)氏の研究で「感情やトラウマ体験を日記に書いた人」は、書かなかった人よりもストレスが減少し、免疫力も高まった」という結果が出ています。
【主な研究結果】
- 表現的ライティング研究(1986年)
- 免疫力の向上:Tリンパ球の反応性が高まり、免疫力が強化さた。
- 医療機関の受診回数の減少:実験後の数か月間で、体調不良で医師の診察を受ける回数が減少した。
- 心理的健康の改善:抑うつ症状や不安感が軽減された。
- 1日約15分間の日記を4日間継続することで効果が見られた。

パワハラを受けた時の、あの最悪な感覚は絶対に思い出したくありませんよね…
しかし、嫌なことを忘れようとするよりも、真剣に向き合って、改めて日記に書き起こして想起することで、上記のような効果が得られるんですね!
拙者も何気なく日記を書いていましたが、このような科学的な効果があるとは初めて知ったでござる(笑)
自己認識と自己肯定感の向上
日記を書くことで、自分の感情や思考を明確にし、自己認識を高める効果があるとされています。
ある研究では、日記を通じて自己の感情や経験を振り返ることで、自己理解が深まり、心理的な成長が促進されることが示されました。
自分の「考えのクセ」「反応のパターン」が客観的に見えることで、「自分を責めすぎていた」と気づけ自己肯定感に繋がるのです。
【主な研究結果】
- Written Emotional Disclosure(WED)と自己肯定感の関係(2011年)
- 158人の女性(18〜22歳)を対象にした実験で、感情的な出来事について日記を書いたグループでは4週間後に自己肯定感が向上した。
- この研究では、感情的な出来事を言語化することが、自分を“観察者の目線”で見られるようになり、メンタルの強靭さ(レジリエンス)が鍛えられることを示唆された。

ここは非常に重要なポイントですね!
日記を書き続けることで、自分を「客観的」に見ることができるんですね!
当時の感情を改めて日記に書き起こし振り返ることで、その時に気づけなかったことや今後の反省点などが理解でき、自己成長につながるというわけですね!
効果的な日記の書き方

効果的な日記の「書き方」と「書く内容」について分けて説明していきましょう!
書き方
- 書く頻度:週に2、3回程度!
- 書く時間:寝る前が効果的!
- 書く量:1日5〜10分、3〜5行でもOK!
- 書き方:手書きが効果的!
書く頻度について
2007年Pennebaker氏 & Chung氏による研究では、「週に数回」日記を書くことで、免疫機能向上、ストレス軽減、心理的回復が促進されるという研究結果が示されています。
慣れないうちに日記を毎日書くと、嫌なことを思い出しているうちに「感情疲労」を引き起こしネガティブ思考が優位に働く可能性があるため、適度な頻度(週2~3回)をおすすめします。

拙者は日記を書き始めて、既に約10年近くになります。
そのため、現在は毎日日記をつけて1日を振り返っています!
しかし、確かに不慣れなうちは、嫌なことを悶々と思い出してしまい感情疲労が起こるものですので、無理は禁物!
まずは週に1回の日記習慣から身につけましょう!
書く時間について
2009年Walker氏による研究では、就寝前は1日の出来事を振り返る時間帯であり、記憶の定着・統合(レミニセンス効果)に適しているという結果が示されています。
夜は副交感神経が優位になる時間帯のため、冷静に今日の自分を客観視して振り返ることができます!
また、夜に1日を振り返り感情を整理することで「入眠がスムーズになった」という研究結果もあるみたいですよ!
書く量について
1986年James Pennebaker氏による研究では、「1回15〜20分、連続して日記を書くこと」によりストレス軽減・免疫強化・抑うつ症状の軽減の効果が見られたと示されています。
書く時間が短すぎると感情処理が浅く、長すぎると反芻思考に陥る可能性があるため、10~20分が適切なバランス。
書き方について
手書きで日記を書くことにより、脳の前頭前野・海馬・運動皮質などが活性化され、記憶の定着・感情の整理・ストレス緩和などさまざまな効果があるという研究結果が示されています。
Mueller & Oppenheimer (2014)
Mangen & Velay (2010)
パソコンやスマホのアプリ等で手軽に日記を書くことができると思いますが、効果を考慮すると手書きに軍牌が上がることになります!
何を書けば良いかわからない…という方に!!
もしこのような状況に陥っていれば、これを参考にしてみてください!
- 今日あったこと(事実)
例:「上司に『遅い』と強く叱られた」 - そのときの気持ち(感情)
例:「悔しい」「情けない」「自信がなくなった」 - その気持ちの原因(思考)
例:「またミスしたらダメだと思い込んでいた」「上司に嫌われてると思ってしまった」 - 別の見方・声かけ(リフレーミング)
例:「上司が厳しいのはその人の性格」「自分がダメだとは限らない」「よく耐えた、自分エライ」 - 今日の自分への一言
例:「今日もよくがんばった」「しんどい中でも出社した、それだけでOK」

これは、ほんの一例でござる!
日記は何を書いても良いんです!
「何もかけないからどうしようと焦っている」という気持ちでも良いですし、腹が立った感情を殴り書きしてもいい、本当に何を書いても良いんです!
その感情を数年後に見返した時に「あ〜この時、こういうふうに感じていたんだな」と思える日が必ず来ます!
まとめ
パワハラで傷ついた心は、誰にも言えず苦しみを抱え込みがちです。
そんなとき、感情を吐き出し、冷静に自分を見つめ直せる「日記」は強力な味方になります。
科学的にも効果が認められており、心の整理・自己理解・ストレス耐性の向上につながる手軽なセルフケアです。
まずは今日から、3行でもいいので書き始めてみてください。
あなたの心は、少しずつ確実に楽に、そして強くなっていくはずです。
市之丞からのメッセージ
以上、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
本ブログでは、パワハラを受け一時は休職に追い込まれた拙者の苦い体験談をふんだんに紹介しています。
憎きパワハラ上司に下剋上するため、徹底した自己啓発を行い、メンタル強化のためのトレーニングをして、論破できるための戦う心理学を学んできました。
その上で、読者の皆様に「パワハラに負けないメンタル必勝法」と「戦う心理学」を伝授し、今よりもより良い人生を歩んでいただくことを目的として、当ブログを運営しております。
今、辛い毎日を送っている方へ。
あなたは一人ではありません。
拙者も、今でも日々パワハラを受けている身…
少しでも読者の皆様の心が軽くなり、前向きになれるヒントをお届けできれば幸いです。

「勇気とは、恐怖を感じないことではない。恐怖を感じながらも行動することだ。」(作家マーク・トウェイン)
昨日よりも今日、今日よりも明日、一歩ずつより良い明日に向かって進んでいきましょう!
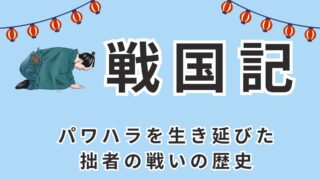
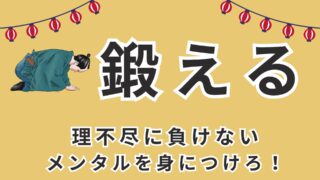

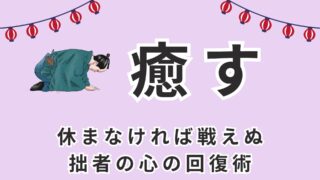

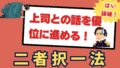
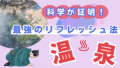
コメント